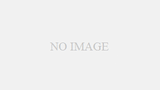こんにちは、まさおです!
AIによるコーディング支援ツールと聞いて、多くの方はGitHub Copilotを思い浮かべるのではないでしょうか?しかし、今開発者の間で注目を集めているのが**「Cursor」です。その威力は、実際の開発現場でコードを書くスピードを6~10倍**にも引き上げると言われています。
本記事では、AI搭載の次世代エディタ「Cursor」の魅力と使い方を徹底解説します。VSCode互換の使いやすさから、Chat・Composer・Agentといった強力機能、実際の運用ノウハウ、他ツールとの比較まで余すところなく紹介します。
この記事はこんな方におすすめです:
- AIでコーディング効率を劇的に上げたい
- GitHub Copilot以外の新しい開発支援ツールを探している
- Cursorの機能や使いこなし方を詳しく知りたい
この記事を読めば、Cursorがなぜ「最強」と称されるのか、その理由と活用方法がよく分かりますよ!
それでは、どうぞ!
結論(筆者の所感)
月20ドルのサブスク料金に抵抗がないなら、最も優先して課金する価値があるのはCursorだと言っても過言ではありません。それくらい万能なAIエディタです。(ただし、自然言語ですらコードを書きたくないという方は除きます)経営者や戦略的な仕事をしている方にはChatGPT Proも同じくらいおすすめできますが、コスパやUXなど様々な観点で見てもCursorは群を抜いています。私はもうCursor無しでは生きられないと感じるほどです。
Cursorとは何か?
**Cursor(カーソル)**は、Visual Studio Code(VSCode)互換の次世代コードエディタです。VSCodeのキーボードショートカットやコマンドパレット、拡張機能などをそのまま活用できるため、新しく学ぶことが少なく導入のハードルが低いのが魅力です。普段からVSCodeを使っている方であれば、操作感に大きなギャップがなくスムーズに移行できるでしょう。
- VSCodeのテーマやフォント設定をそのまま引き継げる
- VSCodeのショートカットも違和感なく利用可能
これらにより、エディタ乗り換え時のストレスが大幅に軽減されます。
AIコーディング支援ツールとしての位置づけ
「AIコーディング支援ツール」として有名なのはGitHub Copilotですが、Cursorはそれだけに留まりません。開発フロー全体をAIが強力にサポートする仕組みが備わっているのです。
- Chat機能:コードに関する疑問をリアルタイムに解消できる(ちょっとした質問やエラー原因の確認など)
- Composer機能:プロジェクト全体を俯瞰したコード生成やリファクタリングが可能
- Agentモード:AIが自律的にコードを生成・編集し、エラー対応までこなす
このように開発の一連の流れを丸ごと支援できる点がCursor最大の特徴です。私自身もCopilotのユーザーでしたが、Cursorに乗り換えてその便利さに感動し、今では開発の中心に据えています。
ブラックボックスだった部分の仕組み
Cursorでは、プロジェクト全体をインデックス化してコード構造を理解し、そのデータを大規模言語モデル(LLM)と組み合わせることで、プロジェクト全体を踏まえた高度なコード提案を実現しています。一般的にはこれは**RAG(Retrieval Augmented Generation)**と呼ばれる手法で、必要な情報をプロジェクト内から検索し、それをもとにAIがコードを生成する仕組みです。
ファイル全体を見渡してまとめてリファクタリングしたり、関連する複数箇所のエラーを横断的に修正したりできるのは、このRAGによるアプローチが根幹を支えているためと言えます。
ポイント
- AIをうまく活用するには、プロジェクト情報の適切なインデックス化が重要です。
- 同時に、機密情報の扱いには注意が必要です(Cursorにはプライバシーモード等の対策機能があります)。
まずはコード補完:Tab機能による効率UP
他ツール(Copilot等)との比較ポイント
「コード補完」と聞けば、多くのエンジニアはGitHub Copilotを思い浮かべるでしょう。しかしCursorの「Tab」補完機能は、複数行にまたがるコード提案や、カーソル位置のスマートな予測など独自の強化が施されています。
- 複数箇所をまとめて修正する提案をしてくれる
- コード全体の文脈を考慮したリファクタリング案を提示してくれる
- マルチライン(複数行)にわたる補完でも非常に自然
Copilotも非常に優秀なツールですが、Cursorの補完は「ここも一気に直そうか?」と関連箇所をまとめて提案してくれる点が大きく異なります。その使いやすさ・UXの高さが、多くの支持を集めている理由だといえるでしょう。
プロジェクト全体をインデックス化して高精度の補完
Cursorがプロジェクトを開くと、コード全体の解析とインデックス化(索引作成)を自動で行います。これにより、プロジェクト全体の文脈を踏まえた高度なコード補完が可能になります。
- 関連するクラスや関数を正しく参照したコード提案ができる
- プロジェクト特有のコーディングスタイルや命名規則に沿った補完が行われる
- 大規模プロジェクトでも横断的に最適なコードを提示できる
もし大規模なリポジトリに新たにCursorを導入する場合は、このCodebase Index(コードベース全体のインデックス化)が正しく機能しているかを事前に確認しておくと良いでしょう。Cursorのセキュリティ情報やインデックス機能の詳細は、公式サイトのセキュリティ説明ページに言及されています。
Codebase Indexとは?
コードベース内のファイルを分析・整理し、検索やコード理解に役立つインデックスを生成する機能です。Cursorではこのインデックスを活用することで、AIによるコード補完の精度を高めています。
CursorのCodebase Indexingはどう動作するのか?
- コードベースをチャンク化
コード全体を構文的に関連する小さな単位(チャンク)に分割します(tree-sitterなどのツールを使用)。 - コードの埋め込み(Embedding)
分割したコード片をベクトル(数値データ)に変換し、リモートのベクターデータベースに保存します。このとき、ファイルパスや行番号などのメタデータも合わせて保持します。 - ローカル/リモートのストレージ
埋め込みデータはリモート側に保存されますが、実際のコードそのものはCursorのサーバー上に送信・保存されません。ローカルモードを有効にすると、コードを一切クラウドに送信しない運用も可能です(ただし埋め込みデータ自体はリモートDBに残ります)。
Codebase Indexを活用する主な機能
- 自動同期:コードベースに変更があるたびにインデックスを自動更新し、常に最新状態を保ちます。
- インデックス除外:.gitignoreや独自の設定で、特定のファイルやディレクトリをインデックス対象から外すことができます。
- プライバシー保護:機密情報や個人情報をインデックス/送信対象からブロックするヒューリスティック(Heuristic Scrubbing)機能があります。
複数行補完・スマートリライト・カーソル予測のメリット
複数行補完
コード入力中に、次に記述しそうな数行分のコードをまとめて候補提示してくれます。これにより、
- 繰り返し処理などのボイラープレートを一括で生成してくれる
- テストコードや型定義まで含めた包括的なコード提案が行われ、作業時間を大幅短縮できる
Tab補完が既存コードのリファクタリングを提案する場面もあります。たとえば、変数名の変更に合わせて関連箇所を自動修正する提案や、より最適化されたロジックへの書き換えを提案してくれることもあります。最初はこのスマートリライトに違和感を覚えるかもしれませんが、意識的に使い慣れることで、今ではCursorのTab補完無しでは物足りなく感じるほど強力な機能だと実感しています。
カーソル予測
複数行補完の「次」を見越して、次に編集すべき箇所へ自動でカーソルを移動させる提案も行われます。細かな調整や後続の追記作業にシームレスに移れるため、コーディング中のリズムが途切れにくくなるのが嬉しいポイントです。
Composer(Normalモード)でのコード生成・編集
Composerモードとは?
Cursorには**「Chatモード」と「Composerモード」**の2種類があります。ここで紹介するComposerモードは、主にコードの生成や編集に特化した専用ビューです。特定のファイルに限定されず、広めの画面でまとまった指示をAIに与え、新しいコードの生成や既存コードの大幅な修正・リファクタリングを行えます。
Chatモードとの違い
- Chatモード:コードやファイル構造の「探索・理解」に適しており、クイックなQ&A(質問回答)に向いている
- Composerモード:より大きなコード生成や段階的なリファクタリングなど、実装作業が主目的
Composerモード画面を開き、指示を入力してEnterを押すと、AIがコードを生成し、そのままファイルへ適用できるという一連の流れをスムーズに行えます。
Normalモードでの基本的な使い方
ComposerにはNormalモードとAgentモードの2種類があります。まずは基本であるNormalモードの活用方法から見ていきましょう。
コード生成のフロー
- Composer画面を開く(ショートカット:
⌘I→⌘Nなど) - 要件や目的を文章で記述する(例:「ReactでToDoリストのコンポーネントを作って」)
- AIが提案するコードを確認し、必要に応じて追加の修正指示を与える
- コードが完成したらApplyボタンでファイルへ直接反映する
この流れだけでも、非常に高速に新機能の雛形を作成でき、同時にコード品質の確保にも役立ちます。
リファクタリングやエラー修正
Normalモードでは、既存コードの一部を選択した上で「リファクタリングして」や「バグを修正して」と指示を出すことも可能です。AIはプロジェクト全体の文脈を踏まえながら修正案を生成するため、連鎖的に関連ファイルまでまとめて編集してくれる場合もあります。
Diff確認と適用
AIが生成・修正したコードは、直接ファイルに書き込まれる前に**差分(Diff)**が表示されます。エンジニアが内容を確認した上で「そのまま適用する」か「一部だけ取り込む」かを選べるため、安全性の面でも大きなメリットがあります。
自動生成される変更範囲が大きい場合は、直前にコミットしておく(作業を一旦保存しておく)と安心です。細かなDiffをチェックし、問題がなければ一括でMerge、あるいは一行ずつApplyして反映するとよいでしょう。
コードとドキュメントを同時に管理するメリット
Cursorには**@docs**などのコマンドを使って、外部ドキュメントを参照しながらコーディングできる仕掛けがあります。これは特にプロジェクトが複雑になってきたときに威力を発揮する便利な機能です。
例えばComposerでコードを書いている途中、@メンションで指定したドキュメントのパスを入力することで、仕様書や外部ライブラリのリファレンスを参照しながら実装できます。仕様があやふやな場合でも、@docsに登録しておいた資料にすぐアクセスして確認しつつ進められるため、チーム開発においても重宝します。
Composer Agent(Agentモード)の衝撃
「AIが主体、開発者が補助」へ発想を変える
Composerモードの中でも最大の目玉と言えるのが、このComposerのAgentモードです。Agentモードに切り替えると、AIがより自律的にコードを書き進めたり、必要なライブラリをインストールするコマンドまで提案してくれます。
- 「〇〇という機能を作って」と指示すると、AIが複数ファイルにまたがるコードを一気に生成・修正
- 実行中にエラーが発生してもAIが検知し、自動で修正案を再提案
- ターミナルコマンドも含めて実行を提案してくれる(実行前には確認プロンプトが表示されます)
これによって、まるでペアプログラミングの相棒が自動で手を動かしてくれているような感覚になります。開発者はコードレビューや微調整に注力し、提案を調整・承認するだけで大半の実装が進んでいくという衝撃的な体験が得られます。
“0→1”の開発で学習していく感覚
特にゼロから新規プロジェクトを立ち上げる(いわゆる0→1開発)段階では、Cursorがプロジェクトをインデックス化しつつ、どんどんそのプロジェクトに詳しくなっていくような挙動を見せます。もちろん内部的にはプロジェクトの変更点を常に追跡しているだけですが、まるで「このプロジェクト用語を理解し始めた!」と感じる瞬間があるほど、自然な提案が増えていきます。
- ランディングページを作成すると、新規ファイル群を自動生成してくれる
- バックエンドにREST APIを追加するとき、既存のエンドポイントを参照しつつ同系統の新エンドポイントを実装してくれる
- データベース定義もAIが把握しているので、関連するマイグレーション(スキーマ変更)まで提案してくれる
このように、AIがプロジェクトに馴染んでいくような印象を持てるのがComposer Agentの面白いところです。
中〜後半の大規模プロジェクトもカバー
0→1の初期段階はもちろん、数ヶ月〜数年スパンの大規模プロジェクトにおいてもAgentモードは威力を発揮します。Agentにドキュメント生成も任せながら開発を進めれば、
- 機能を追加する際に自動で関連クラスやAPIを修正してくれる
- エラーが起きればAIが原因を検知して修正案を提示してくれる
- 大量のファイルにまたがる横断的なリファクタリングも一気に実行してくれる
ただし、プロジェクトが大規模になればなるほどAIも誤りを起こすリスクがあるため、こまめなGitコミットやテストの充実が必須です。AIが提案したコードを鵜呑みにせず、差分チェック→取り込み→テストのステップを常に挟むようにしましょう。
どこまで任せるか? 使用時のベストプラクティス
Agentモードをチームで安全かつ効果的に活用するために、以下のようなポイントを事前に取り決めておくと良いでしょう。
- チーム全体でAgentモード使用のガイドラインを共有しておく
- 「Agentモードをどの段階で使うか」「どの程度の権限を与えるか」を決めておく
- ターミナルコマンドの自動実行を許可するかどうか(YoloモードのON/OFF)も事前に取り決める
- AIが生成したコードのレビュー&差分チェックを徹底する
- AIがコードを大幅に書き換えた場合は必ず人間がレビューする
また、テストコードも同時に生成させ、テストが通ったらコミットするというサイクルを確立しておくと安心です。こういったルールをチームで明文化しておけば、Agentがもたらす破壊的変更のリスクを抑えつつ、快適に運用できるでしょう。
RAGによる“賢さ”の秘密(推測)
なぜ「プロジェクト全体を理解した回答」ができるのか?
Cursorは独自のコード検索エンジンを備えており、ChatGPTやClaudeといった大規模言語モデル(LLM)と連携して回答を生成しています。これは典型的な**RAG(Retrieval Augmented Generation)**のフローに近く、
- プロジェクトから関連情報をまず「検索」し、
- 言語モデルが検索結果をもとに回答を「生成」する
という段階を踏んでいるため、プロジェクト内の特定ファイルにしかない関数名や情報でも正しく参照した回答が可能になっているのです。
質問やコマンドへの高精度な対応
Cursorでは**@codebaseや@docs**といったコマンドで、AIに参照してほしいコンテキストを明示的に指定できます。「このエラーメッセージに関連するファイルを探して」と頼めば関連ファイルを検索し、「@folders」でフォルダ構成を確認するといった、複数ファイルにまたがる文脈を踏まえた提案も可能です。
汎用的なChatGPTなどと異なり、Cursorはユーザーが扱っている生のコードに直接アクセスできるため、回答の精度が格段に高くなるのです。
デメリット・課題
もちろん課題もあります。まず、プロジェクト規模が非常に大きい場合はインデックス化に時間がかかる点です。また、AIが誤解に基づいてコードを修正してしまうリスクも否めません。引数やクラス構造の変更を一気に適用しすぎると、意図せぬ破壊的変更につながる可能性もあります。
とはいえ、適切なガードレール(Gitによるバージョン管理やCI/CDでのテスト実行、ドキュメント整備など)を設けて運用すれば、デメリットよりも得られるメリットのほうが圧倒的に大きいでしょう。
実際の運用ノウハウ
コミットのこまめな切り方
Composer Agentを使うと、複数ファイルにわたる大規模な修正が一気に行われることがあります。そのため、こまめにコミットすることが非常に大切です。以下のポイントを意識すると良いでしょう。
- Agentに大規模リファクタリングを依頼する前に、一度コードをコミットして区切りの良い状態にしておく
- 差分が大きくなりすぎる場合はブランチを分けて作業する
- マージ前にはテストをしっかり実行する(予期せぬ不具合が混入していないか確認する)
万が一「思っていたのと違う」という結果になっても、コミットが細かく分かれていれば容易にリバート(巻き戻し)できます。
Composer Agent+ドキュメント生成フロー
要件定義の段階から、まずComposerでざっくりと仕様ドキュメントを作っておきます。その上でAgentモードに切り替え、「この仕様に沿ってコードを書いて」とAIに指示して開発を進めます。
開発途中で仕様変更が発生した場合は、ドキュメント自体も更新してからAgentにコード修正を依頼します。そして仕上げの段階では、AIにコードとドキュメントの整合性を取るよう整形・修正させます。
つまり、「コードを書いてからドキュメントを書く」のではなく、AIを使ってコードとドキュメントを同時並行で進めるというスタイルです。結果的にドキュメントの未整備(ドキュメント負債)を溜め込まずに済むポイントになります。
チームでの活用ポイント
- Businessプランでは組織管理機能やSSOログイン、プライバシーモード強制などセキュリティ設定が充実しています。
- チーム全員がCursorを使うなら、Notepad機能でメモを共有したり、Docs機能で共通のドキュメントを参照できる運用が便利です。
- 大規模リポジトリでは、不要なフォルダや生成ファイルを**.cursorignore**で除外し、AIが混乱しないよう工夫することが必須です。
まだある!Cursorが持つその他の強力機能
Notepad / Docs機能でのナレッジ共有
CursorにはNotepadと呼ばれる機能があり、Markdown形式でメモを取ってAIに参照させることができます。プロジェクトの要件やサンプルコードをNotepadに蓄積しておけば、
- 「@Notepad」と入力するだけでいつでもメモをAIに参照させられる
- チームメンバーとNotepadを共有すれば、共通のベストプラクティス集として活用できる
またDocs機能で外部のドキュメントやAPI仕様書を登録しておくと、AIがそれらのドキュメントを直接参照しながらコードを生成してくれます。社内Wikiや外部サービス上の資料も、URLを指定するかテキストとして追加することで参照可能です。
.cursorignore / .cursorrules でのきめ細やかな制御
- .cursorignore:インデックスから除外したいファイル・フォルダを指定し、不要なノイズを除去できます。
- .cursorrules:プロジェクト固有のコーディング規約やAIの出力スタイルを定義できます。
例えば.cursorrulesには以下のようなルールを記述できます:
- 「Reactのコンポーネントは
src/components/配下に配置する」 - 「変数名は英語でスネークケースに統一する」
こうしたプロジェクト固有のルールを明示的に定めておくことで、AIのコード提案を自分たちのチーム文化・コーディング規約に沿った形にチューニングできるようになります。
ちなみに、cursor.directoryというサイトでは、他のユーザーが使っているcursorrulesの例を見ることができます。また、私のLINE@に登録すると、私が実際に使っているcursorrulesファイルを無料で共有しています。
【2025/02/25追記】
新機能としてProjectRulesが登場しました(イメージとしては、cursorrulesがプロジェクト全体用、ProjectRulesが個別詳細用です)。詳しくはこちらの記事で解説しています。
Privacyモードやログ取得制御で安心運用
Cursorはセキュリティ面でも配慮されており、SOC 2認証を取得しています。プライバシーモードを有効にすれば、コードが基本的にクラウドに送信されることはありません。Businessプランであれば、全ユーザーにプライバシーモードを強制するなど、組織全体でセキュリティを高める運用も可能です。機密性の高いプロジェクトでも安心してAIの恩恵を受けられるのは、エンタープライズにとって大きな意義と言えるでしょう。
Gitメッセージ自動生成機能
CursorのGitメニューには「✨」アイコンがあり、ここをクリックするとコミットメッセージをAIが自動生成してくれます。地味に便利な機能で、コミットメッセージを考えるのが苦手な人にとっては大きな助けになるかもしれません。
MCPサーバー
Cursorには、よく使うワークフローと連携できるMCPサーバーという機能もあります。例えばJenkinsなどCIツールとの連携も可能で、詳細はこちらの記事で解説されています。
【宣伝】
Cursorをフル活用してAI駆動のサービス開発を行うためのノウハウを、一つの記事にまとめて公開しています。企画・設計・開発・マーケティングまで広く網羅し、技術面(特にCursorの使いこなし)では、Composerに実際に投げたプロンプト例を含むソースコードを2プロジェクト分共有しました。興味のある方はぜひご覧ください。
※ 詳細はこちらのNote記事をご参照ください。
料金プランと導入検討
Hobby, Pro, Businessプランの違い
Cursor公式サイトによると、主に3つの料金プランが提供されています。
Hobby(無料プラン)
- 月間約2,000回までのコード補完(Completions)が利用可能
- GPT-4oなど高性能モデルは月50回程度の「低速リクエスト」のみ使用可能
- Proプランの2週間無料トライアルが付属
Pro(20ドル/月)
- コード補完が無制限に利用可能
- GPT-4oやClaude 3.5 Sonnetなどのプレミアムモデルを、高速リクエスト500回+低速リクエスト無制限で使用可能
- 自分の開発スタイルに合わせて、Cursorの全機能を存分に活用できる
Business(40ドル/ユーザー/月)
- Proプランの全機能に加えて、組織全体でプライバシーモード強制やSAML/SSOといったセキュリティ強化機能を利用可能
- 管理者向けダッシュボードや利用状況の統計情報が提供される
- 大規模チームや機密プロジェクトでの導入に適したプラン
本格的にComposer Agentの真価を体感しつつガッツリ使い込みたいのであれば、実質的にProプラン以上の利用が必要になるでしょう。
チーム単位で導入するメリット
Cursorをチーム・組織単位で導入すると、例えば次のようなメリットがあります。
- コードレビューやドキュメント整備をAIに一貫してサポートさせられる
- Businessプランならポリシー設定や支払い管理を一括で行える
- セキュリティリスクやプライバシー管理を集中制御しやすい
特に、AIによる大量のコード自動生成を複数人でフル活用する場合は、Businessプランの中央管理機能が非常に便利です。
GitHub Copilot他との比較
GitHub CopilotはVSCodeやJetBrains系など多くのIDEで利用できる点が強みですが、複数ファイルにまたがる自動化(エージェント)機能は限定的です。
一方CursorはVSCode互換エディタ上で動作するためUI/UXがVSCodeに近く使いやすい反面、他のIDEでは利用できない制約があります(※執筆時点)。しかし、Claude 3.5 SonnetやGPT-4oといった複数のLLMを状況に応じて使い分けられる点もCursorの長所と言えるでしょう。
結局のところ、エディタとの一体感やプロジェクト全体の文脈を理解した自動化機能を求めるならCursorに軍配が上がるでしょう。一方で、使うIDEの選択肢を広く保ちたい場合はCopilotや他のツールを検討する余地があるかもしれません。
さいごに
Cursorは単なる自動コード補完ツールではなく、プロジェクト全体を理解して動いてくれる**“AI参謀”**と言っても過言ではありません。特にComposer Agent機能を使いこなし、チームでの運用ルールをきちんと整備すれば、劇的な生産性向上が実現できるはずです。
例えば次のような効果が期待できます:
- コーディングに費やす時間を短縮し、実装サイクルを高速化できる
- AIと協調してドキュメントも並行して更新されるため、ドキュメント負債を削減できる
- 浮いた時間をコードレビューやテストに充てられるので、最終的なコード品質が向上する
Composer Agentは非常に強力(ある意味破壊的)な機能ですし、またClaude 3.5 Sonnetの使いやすさも相まって、私としてはProプラン以上の利用を強くおすすめしています。
もし「Proプランまでお金を払う価値があるかピンと来ない…」という場合でも、実際に数日間使い続けてみれば「このプロジェクトはもうAIなしでは進められない」と感じるかもしれません。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます!今後もAI分野の新しい活用方法や開発テクニックを、X(旧Twitter)でいち早く紹介していきます。少しでも興味を持たれましたら、ぜひフォローして最新情報をチェックしてくださいね。